『言葉を失った国の記憶』
気がつけば、日本語が軽くなっていた。
詩のような手紙も、深い祈りのこもった挨拶も、もう聞かれない。今の主役は「チーカワ」だ。擬音とスタンプ、三語で済む会話。それは「進化」なのか、それとも「忘却」なのか。
しかし、思えばそれも仕方ない。
かつては林房雄、西部邁、森鷗外、太宰治、三島由紀夫――多くの知識人・国士たちがこの国の「空気」に絶望し、死を選んだ。
彼らが戦ったのは外敵ではない。何も語らせず、誰も立たせず、ただ沈黙と同調だけが美徳とされるこの“空気病”だった。
日本は美しい国だった。
温泉で体を洗い、畳の上で季節を感じ、発酵を味わい、雨に黙する。その背後には、勤勉と礼節、そして「言葉」があった。人と自然の間をとりもつ、繊細で豊穣な日本語が。それが今、擬音と顔文字に圧縮されていくのは、文化の終末の徴かもしれない。
外の文明はどうか。
欧米は支配と競争の文明、中国は恐怖と同化の文明、韓国は情と計算の文明。どれもある意味で強いが、どこか粗い。日本はそのどれでもなく、譲り合いと沈黙、余白と祈りの文明だった。
だからこそ、外国人が増えれば日本は確実に変わる。変化とは「融合」ではない。「溶解」か「崩壊」だ。そしてその先に、新しい“何か”が始まるのかもしれない。
だが、そう思ってしまう自分がいる。
「日本はいちど滅びるのがいい」と。
美しいものが崩れ、言葉がなくなり、土地も譲られ、空気が変わりきったそのあとに――
それでも、なお芽を出す何か。
それを見届ける目と、言葉を紡ぐ者が、どこかに残っているなら。滅びることさえ、希望になるのかもしれない。
私たちの時代は、その橋のたもとにいる。
終わるものを悼みながら、何かを託す最後の世代だ。

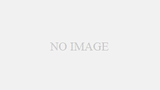
コメント